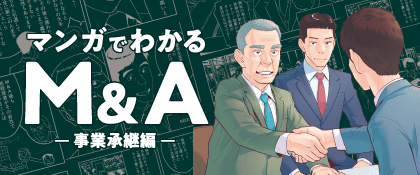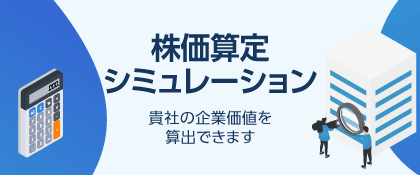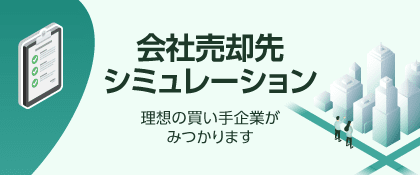【M&A】「売った後」「買った後」で見えた、予想外の未来

M&Aと聞いて、あなたはどのようなイメージを抱くだろうか。 失意とともに会社を手放す「売り手」経営者。数字のみを求める冷徹な「買い手」経営者。そして、間をとりもつ怪しげな仲介会社──。 もしかしたら日本には、そのようなM&Aもあるのかもしれない。しかし、本取材で目にしたのは、「冷たい金融取引」ではなく「温かい人生の承継」としてのM&Aだった。 会社を「売った」側と「買った」側。経営者の決断の裏にあった葛藤、M&Aプロセスで得た気づき、そしてM&Aが切り拓いた予想外の未来とは。 経営者に寄り添い、支え続けたM&Aコンサルタントによる専門的解説も交え、M&Aの人間的側面と具体的な価値をひもとく。
※本記事はNewsPicksに掲載された記事(https://newspicks.com/news/15314205)の転載です。

シェア7割を誇る会社を譲渡した理由
江戸時代に佐倉藩の城下町として栄え、蘭学の先進地として「西の長崎、東の佐倉」と呼ばれた千葉県佐倉市。この地に工場を構える高木ゴム工業(本社は習志野市)の取締役社長・松﨑隆一さんは、2024年11月に大阪を拠点とする株式会社GWEに会社を譲渡した。
M&A時も現在も、高木ゴム工業の業績は順風満帆。主力製品である食品飲料プラントのプレート式熱交換器に使われるゴムパッキンは、市場シェアおよそ7割を誇っている。
「コンビニに冷蔵庫がドンとありますよね。その中に並んでいるペットボトル飲料のうち、ざっくり6〜7割は弊社のパッキンを使って生産されています」(松﨑氏)

松﨑さんが3代目として父から事業を承継したのは、バブル崩壊後。当然、世間は不景気だった。
「現状維持がやっとという経営状況。おまけに大手企業が市場に参入してきて、食品飲料プラントの仕事を根こそぎもっていかれました」(松﨑氏)
当時、従業員は30名ほど。小さいころから工場に出入りしていた松﨑さんを、「隆ちゃん」と呼ぶベテランもいた。このまま会社を終わらせるわけにはいかない。
窮地を救ったのは、入社まもないころに松﨑さんが主導して始めた新しいゴム素材の研究開発だった。
「お客さんのニーズにこたえるため、よりよい製品をつくるための研究開発が実を結び、新素材が次々とフィールドテストに合格しました」(松﨑氏)

新素材の開発によって、高木ゴム工業は息を吹き返した。市場を取り戻すことに成功し、シェアは7割に達した。
ここでひとつ疑問が浮かぶ。苦労の末に立て直し、経営も好調な会社をなぜ譲渡しようと考えたのか。
「M&Aを考え始めたのは、40代後半になってから。後継者をどうするかに悩んでいました。私には娘が3人いるんですが、同じような苦労はさせたくはない。娘たちには一切、会社の経営に関与させていませんでした」(松﨑氏)
そんな折、融資を受けるメインバンクからとあるM&Aコンサルタントを紹介された。日本M&Aセンターの河内孝裕さんだった。

若く、弁の立つ河内さんの第一印象は「チャラい」だった。
「とにかくしゃべりがうまいんですよ。だいたい怪しいじゃないですか、そういう人に限って(笑)」(松﨑氏)
当時、高木ゴム工業にはM&A仲介会社から多くの営業電話があった。そんな時代背景もあり、初めは少し警戒した。ただ、河内さんは大手金融機関と提携する日本M&AセンターのM&Aコンサルタント。なにより人柄を知って、すぐに信頼できると確信した。
「M&Aを目的とするのではなく、松﨑社長、従業員のみなさん、そして娘さんたちにとっていちばんいい事業承継はどのような形なのか。社長の考えをお聞きしつつ、まずはM&Aへの理解を深めていただくことから始めました。
とくに強調してお伝えしたのは、M&Aはあくまで株式と個人保証の承継であるということです。一般的に会社を譲渡した経営者は引退するといったイメージがあると思うのですが、それが絶対というわけではありません。
元気なうちにM&Aを終え、引き続き社長として会社をけん引する。それが最近のM&Aの潮流であると」(河内氏)

「買い手」候補リストを手渡されたときは、さすがにビビりました
M&Aをするにあたり、松﨑さんが「買い手」企業に求めた条件がふたつあった。ひとつは、ゴム製品を製造する同じ業界の企業であること。もうひとつは、事業規模が同じくらいの企業であること。
「弊社は飲料品のプラントを支えている会社です。つまり、私たちがつくるゴム製品は生活者の健康に直結し、社会的責任がとても大きい。異業種の会社だと、それを理解してもらうのは難しいと考えていました。
また、相手が大きすぎると数年で会社を清算されてしまうかもしれません。弊社のシェアは7割あります。そうなればクライアントや生活者に迷惑をかけてしまう。だからこそ、同じ規模でこの先20年、30年と協力して事業を続けられる会社であることが重要でした」(松﨑氏)

理想はM&A後も、対等な目線で高木ゴム工業とともに歩んでくれる会社。その共通認識のもと、「買い手」候補のリストアップが始まった。「買い手」候補リストを手渡されたときの松﨑さんの心境は、「さすがにビビりました」だった。
「具体的な企業名が並んでいて、一気に現実味を帯びてくるんです。『やっぱりM&Aやめようかな』とも思いましたし、それからは悩みっぱなしです。正解なんてないわけですし」(松﨑氏)

3代続いた会社を売る──。取り引き企業に迷惑はかけられない。なにより、従業員の未来がかかっている。そんな中、大阪のある企業が名乗りをあげた。株式会社GWE。ゴム製品を製造する企業で、事業規模も理想的だった。
「『ぜひ弊社が』と真っ先に手をあげてくださったのが、GWEの代表取締役である毛利社長でした。トップ面談では猛暑の日にもかかわらず、3ピースのスーツ姿。ものすごい熱意で面談に臨んでくださいました」(河内氏)
「売り手」と「買い手」。ふたりの経営者は、初対面から意気投合した。トップ面談を終え、その足で工場を見て回った。
「毛利さんの第一印象はバッチリでした。私は人見知りなほうなんですが、すぐに話が合いそうだと感じました」(松﨑氏)
「初対面の日に工場を見学するケースはめったにありません。私の目には、おふたりがすでに仲のいい友人として映っていました」(河内氏)

その後の展開は早かった。トップ同士の情熱が合致し、トップ面談からわずか3カ月で両社のM&Aは成立した。その要因はなんだったのか。
「おふたりの決断力あってのことですが、いま思い返しても両社はベストマッチでした。もし、あと1〜2年をかけて相手企業を探したとしても、GWEさん以上の企業はなかったと思います。
M&Aコンサルタントとして心がけたことは、高木ゴム工業という会社をとことん理解すること。事業内容はもちろん、松﨑社長の想いと会社の歴史を『企業概要書』という提案資料にしっかりと落とし込み、GWEさんにお届けしました。
また、どれだけいい縁であっても金額が合わなければM&Aは成立しません。高木ゴム工業はどのくらいの株価になるか。松﨑社長にしっかりご説明し、ご理解いただく。そういった仕事を愚直にやり通すことが、私の仕事でした」(河内氏)
会社を売って、拓けた未来
「ふたりで伝えましょう」。M&A成約式の後、松﨑さんと毛利さんは揃って高木ゴム工業の従業員たちの前に立った。
「本社とふたつの工場、1日に3カ所を回って今後について説明しました。毛利さんと話したのは、ネガティブな変化は起こらないということを、これからいっしょに従業員たちに見せていこうということです」(松﨑氏)
代表権は移ったものの、取締役社長として松﨑さんはいまも変わらず高木ゴム工業をけん引している。ネガティブな変化は起きていない。ただ、ポジティブな変化はあった。
「弊社がつくるゴム製品は巨大なものが多く、つくるまでに数カ月はかかります。一方で、GWEさんは1日に何万個もつくっている。もちろん、両社がつくるゴム製品は用途も違えば大きさも違います。ただ、毛利さんは大きなゴム製品をつくるにしても、省力化、自動化は実現できるはずだと」(松﨑氏)

現在、高木ゴム工業は従業員が一体となって、変革の時を迎えている。新たな機械を導入し、自動化をすすめ、佐倉と成田にある工場の役割を明確にした上で効率化をすすめている。
「第三者の目を通すと、私たちが気がついていなかった課題が見えてくる。従業員のみんなも私の意識も変わってきました。本当はもう少し早く引退したかったんですが、逆にやるべきことが増えてしまいましたね(笑)」(松﨑氏)
いま、高木ゴム工業のように経営が順調にもかかわらず、会社を譲渡する企業が増えている。その背景には、進む高齢化によって経営者が70代以上の企業が98.6万社、60代の企業が79万社にのぼるという事実※がある。
「日本でもM&Aという言葉はすでに認知されました。ただ、本質はまだまだ理解されていないと思います。高木ゴム工業様とGWE様のような、温かいM&Aをつないでいくこと。日本全国の経営者のみなさんが黒字廃業する前に、M&Aという選択肢を届けることが、私たちM&Aコンサルタントの使命だと考えています」(河内氏)
※出典:中小企業庁「中小M&A市場改革プラン 中小M&A市場の改革に向けた検討会 中間とりまとめ」経営者年齢別 中小企業・小規模事業者数の分布


原点となった1社目のM&A
穏やかな瀬戸内海を望む、広島県呉市。この地で祖父が創業した株式会社銀の汐を3代目として承継した大塩義晴さんは、2021年に埼玉県で高級米菓を製造販売する三州製菓株式会社をM&Aで譲り受けた。
「銀の汐は遊技場向けの菓子の製造販売をメイン事業としていますが、全国から遊技場が少しずつ姿を消していくなか、新たな販路を開拓する必要がありました」(大塩氏)

自社でも販路開拓を試みた。また、土産品など商品開発にも力を入れた。だが、どうもしっくりこない。
「そこで選択肢として浮かんだのがM&Aでした。ただ、さまざまなM&A仲介会社の力をお借りして探しましたが、銀の汐との相乗効果が期待できる会社はなかなか見つかりませんでした」(大塩氏)

甘い香りが漂う、銀の汐広第一工場。焼菓子が次々に焼かれていく
そんな中、大塩さんと二人三脚で理想の会社探しに奔走したのが、日本M&Aセンターの諸井拓也さんだった。
「大塩社長が求める会社像を丁寧にヒアリングしつつ、その背後にある事業戦略や成長ストーリーを整理し、それらを補完できそうなお相手を探していきました」(諸井氏)

M&Aの世界において、「売り手」と「買い手」をつなぐことをマッチングと呼ぶ。そしてこのマッチングは、そうやすやすと見つかるものではない。そんなある日、諸井さんから紹介された会社に大塩さんの目がとまった。三州製菓だった。
「大塩社長が求める会社の解像度が上がっていましたから、提案前から三州製菓様とのマッチングには確信がありました。両社が持っていないものを補完し合えるし、間違いなく多くのシナジーが生まれると」(諸井氏)
三州製菓には事業を承継する後継ぎが不在で、未来を見据えともに歩める「買い手」を探していた。一方で銀の汐にとっても、商品ラインナップの拡充や、販路を拡大できる願ってもない「売り手」だった。
「三州製菓さんは、弊社にはないテーマパークや百貨店という販路を持っていました。販路というのは長年にわたって構築された信頼関係をもとに成り立つものです。三州製菓さんとのM&Aがなければ、この販路は決して得ることができなかったはずです」(大塩氏)

自社よりも、大きな「売り手」
両社は相思相愛だった。三州製菓サイドからは、「歴史ある銀の汐を、若くして率いる大塩社長にとても好感を持った」との声があがった。
「銀の汐としても、三州製菓さんほどイメージにピッタリ合致する会社はほかにありませんでした。ただ、最後に印鑑を押すときにふと思ったんです。『三州製菓さん、規模が大きすぎないか?』と」(大塩氏)
三州製菓は従業員200名を超え、銀の汐よりも規模の大きな会社だった。簡単に決めてしまったのではないか。もっと考えるべきなんじゃないか。そんな葛藤もあったが、大塩さんは印鑑を押した。決断の決め手となったのは、当時三州製菓の役員だった斉之平一隆さんの存在だった。
「フィーリングが合ったんですよね。斉之平さんには現在三州製菓の社長をおまかせしていますが、彼といっしょならやっていけると感じたんです」(大塩氏)

諸井さんからの助言もあった。
「M&Aにおいて、自社よりも規模が大きい会社を譲り受けるケースはゼロではありません。また 、M&Aの難易度は企業の規模に比例するものではなく、むしろ、規模が大きい会社ほど組織体制がしっかりしていて、個人に依存していないぶん、引き継ぎがしやすいこともあります。
そうした観点から、三州製菓様は組織基盤が整っており、業務の属人化も少ないと感じていたため、初めてのM&Aでも安心して引き継げるよい組み合わせだと感じていました 」(諸井氏)
とはいえ大塩さんにとって初めてのM&A、当然右も左もわからない。そこで、プロ(日本M&Aセンターグループの日本PMIコンサルティング)の力を借りて推し進めたのがPMIだ。

「とくに重視したのは、お互いの企業文化のすり合わせです。三州製菓さんには三州製菓さんの、銀の汐には銀の汐の文化がある。それぞれのよさを尊重し、活かしつつ、いっしょにやれることはいっしょにやる。無理やり銀の汐の企業文化に統合しようとは考えていませんでした」(大塩氏)
「ともすれば『買い手』側は、『売り手』側を自社の色に染めたいと思ってしまいがちです。しかし、大塩社長は違いました。三州製菓様の企業文化を無理に変えようとしなかったことで、従業員のみなさんも、これまでの延長線上で安心して働くことができたと思います」(諸井氏)
もちろん、人事制度や商品の利益率の算出など、改善すべき部分もあった。しかし、それを伝えるにもお互いに気を遣ってしまう。
「そこで、プロとして日本PMIコンサルティングのコンサルタントに間に入ってもらいました。私たちが直接伝えるとどうしてもニュアンスが強くなってしまうことも、プロが間に入ることで円滑に進みました。M&Aにおいて誰から何を伝えるかは、本当に重要だと感じました」(大塩氏)

会社を買って、拓けた未来
その後、M&A、そしてPMIのメソッドを確立した大塩さんはM&Aを加速させ事業を拡大。新たにミクシオホールディングスを立ち上げ、銀の汐、三州製菓を含め現在は11社を束ねている。しかしなぜ、ホールディングスという形を選んだのだろうか。
「上下関係ではなくて、横並びの対等な関係をつくりたいんです。単純に上と下という関係性が嫌いなんですよね(笑)」(大塩氏)
M&Aといえば、一般的には「買い手」が「売り手」を子会社化することが主流であり、対等な位置づけの兄弟会社として運営するケースは限定的だ。
しかし、「売り手」側のメリットは多い。ブランドや経営の独立性を保つことができ、「売り手」の経営陣や従業員のモチベーション維持にもつながり、結果的に双方にとっていい関係を築くことができる。

会社の応接室には、M&A成約を記念した写真と盾が並ぶ
「M&A は異なる文化や価値観を持つ会社同士がひとつのグループになるということです。最初はお互いに相手への不安や戸惑いがあるのは当然です 。
大塩社長を見ていて驚くのは、お相手の経営者や従業員を心の底から信頼されていることです。『そこまで任せちゃっていいの?』と思うことさえあります。しかしそれが、次々とM&Aを成功させてきた秘訣だとも感じています」(諸井氏)
大塩さんには、いまも忘れられない言葉がある。M&A1社目となった三州製菓のキーパーソンである人物に、「三州製菓を承継していただいて、 ありがとうございました」と声をかけられたことだ。
M&Aは冷たい、悪だ。最初に抱いていたそんな認識が崩壊した瞬間だった。本当のM&Aは、温かいのだと知った。
「私は、従業員のみなさんに“会社のため”に働いてほしいとは思っていません。グループとして、いっしょになった従業員のみなさん一人ひとりにこの会社で働いてよかったと思ってもらえたら、それがいちばんうれしいですね 」(大塩氏)。

撮影:冨田寿一郎
デザイン:堀田一樹[zukku]
編集・執筆:増田謙治